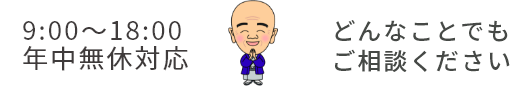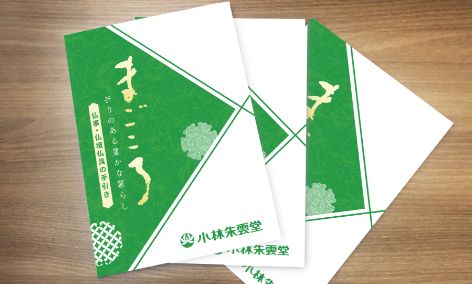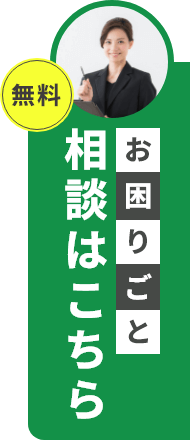8月16日午後6時より岡山市の中心市街地を流れる西川を会場に、岡山市仏教会主催の「灯籠流し」が行なわれます。




・ご参加ご希望の方は、岡山店・原尾島店・青江店で灯籠用紙(灯籠代:前売り900円)をお買い求めください。
・故人の戒名やご当家の先祖代々とご記入いただき、当日下石井公園の受付にお持ちください。
※記入については、当日受付で、お寺の方にお願いもできます。
・受付で灯篭を受け取り組み立てていただきます。
▼2022年の灯籠流し「当日の流れ」をご参考にご覧ください。
・当日会場でも灯籠を購入することが出来ますので、
「灯籠流しを行いたい」「手を合わせたい」と思う方は是非会場へ足をお運びください。
~・~・~・~・~・~・~・~・~
◆灯籠流し(とうろうながし、Water lantern)は、精霊送りの一種で、お盆に死者の魂を弔って灯籠(灯篭)を河川や海に流す風習。
精霊が灯籠に乗って彼方の世界に行くとの思想に基づいている。とうろう流しや灯篭流しとも表記する。
出典:世界宗教用語大事典
~・~・~・~・~・~・~・~・~
▼2022年「RSKイブニングニュース」より
岡山市の中心部を流れる西川で恒例の灯籠流し
▼記事:2024年「岡山 NEWS WEB」NHKより
岡山市中心部で16日夜、恒例の灯籠流しが行われ、集まった人たちがおよそ2500個の灯籠に手を合わせて先祖の霊を供養しました。
岡山市の中心市街地を流れる西川の灯籠流しは、岡山市仏教会が毎年お盆の時期に行っていて、夏の風物詩になっています。
はじめに近くの公園に設けられた祭壇に、先祖の名前や亡くなった人の戒名が書かれた灯籠が並べられ、僧侶たちがお経を唱えました。
そして、紙でできた灯籠の中にあるろうそくに火がつけられ、お経を読み上げる声が響く中、およそ2500個の灯籠が一つ一つ水面に浮かべられました。
訪れた人たちは、夏の夕暮れに次々と川に流される灯籠を見つめ、手を合わせたり写真を撮ったりしていました。
岡山市の60代の女性は、「義理の母親の初盆で来ました。風情ある灯籠流しで生前の出来事を思い出しました」と話していました。
また、小学4年の孫と訪れた岡山市の80代の女性は、「一度にたくさんの灯籠を流してにぎやかに先祖の霊を送ることができていいと思います」と話していました。
灯篭流しの起源と意味
灯篭流しの起源と歴史
灯篭流し(Toro Nagashi)は、日本の伝統的な行事で、特にお盆の期間に先祖の霊を慰め、故人を偲ぶために行われます。
この行事の起源は古く、仏教の影響を受けて日本に広まったとされていますが、その具体的な始まりは確定していません。
伝えられるところによると、平安時代には既に水辺に灯篭を流す習慣が存在していたと言われています。
灯篭流しの歴史を詳しく見ていくと、もともとは中国の灯篭を模したもので、灯篭に火を灯し、水面に浮かべることで、水と火の神秘的な力を使って、霊を浄化し、安らかな彼岸へ送り出すという意味が込められていました。
さらに、地域によってはそれぞれ独自の特色を持った灯篭流しも見られます。
たとえば、京都の鴨川では、五山の送り火と同時期に行われ、その美しさが多くの参加者や観光客を惹きつけています。
このように、灯篭流しは日本各地で異なる形で受け継がれてきた伝統行事であり、それぞれの地域の文化や歴史が色濃く反映されていることが、この行事の多様性と豊かな背景を形成しています。
灯篭流しの文化的意味
灯篭流しは、ただの風習以上の深い文化的意味を持つ日本の伝統行事です。
この行事は、故人を偲び、先祖の霊を慰めるために行われ、参加者にとっては霊的な浄化と心の安らぎを提供します。
灯篭に火を灯し、それを水面に流すことで、生と死、過去と現在が繋がり、自然のサイクルと人間の感情が一体となる瞬間を象徴します。
この行事の文化的意味は、家族やコミュニティの絆を再確認し、共有することにもあります。
灯篭流しに参加することで、生きている者たちは亡くなった人々とのつながりを感じ、故人の思い出を共に語り合い、新たな絆を形成します。
このようにして、灯篭流しは個人的な悲しみや思い出を共有し、社会全体でそれを受け止める場を提供することで、コミュニティの一体感を強化します。
また、灯篭流しは平和と希望の象徴としても広く認識されています。
特に広島での平和記念式典で行われる灯篭流しは、戦争の犠牲者を悼み、世界に対する平和のメッセージを発信する重要な行事とされています。
ここでは、平和への願いや、争いのない世界を望む心が灯篭に託され、水面を通じて広く世界に向けて送られます。
このように、灯篭流しは単なる追悼の儀式を超えて、文化的・社会的に多層的な意味を持ち、参加するすべての人々にとって深い精神的な影響を与える行事となっています。
その背後にある意味を理解することは、日本文化の豊かさと深さをより深く知る一つの鍵となります。